| 視察目次へ戻る |
| 前日へ 翌日へ |
| ●行程 |
| ベルゲン | 終日 |
|
| 事情調査内容 | ノルウェー国立水産研究所アウストヴォル島基地を視察(午前・午後) 担当者 研究所副所長 ●疫病対策、餌活魚養殖、自然環境保全について |
|
| 宿泊ホテル | FIRST MARIN HOTEL ファースト マリン ホテル ℡ 47-53-05-15-00 |
| ●日本への輸出が第一位 |
 ベルゲン市では、ベルゲン大学の渡部州典氏と事前にアポイントをとり、様々な配慮をいただいた。養殖施設には漁病被害の防止もあり、外国人の立ち入りは認めていないのが基本だ。今回は国立の研究施設を、特別に案内・説明をしてもらった。 ベルゲン市では、ベルゲン大学の渡部州典氏と事前にアポイントをとり、様々な配慮をいただいた。養殖施設には漁病被害の防止もあり、外国人の立ち入りは認めていないのが基本だ。今回は国立の研究施設を、特別に案内・説明をしてもらった。(写真は、船を待つ、右から田村道議、佐々木道議、阿部道議、蝦名道議。船着き場の待合室には、島民・買い付け業者・研究者の姿しかみあたらない) ノルウェー漁業は、漁獲量で340万トン・世界第10位、養殖業は内50万トンである。生産物の9割は輸出で、単一国では日本が最大の輸出国となっている。 輸出にあたっては、ノルウェー水産物輸出審議会が大きな力を持ち、全世界の主要マーケットに拠点がある。20カ国以上で販売キャンペーンを行っている。その活動原資77億円は輸出額への課税(0.3~0.5%)でまかなわれている。 日本にはサケ、サバのマーケティング活動をしている。食の安全はEU規則を遵守、ハサップも米国よりは厳しい。漁場から輸出までの全プロセスに、徹底した衛生基準が行われている。 サケの養殖は、特別免許を取得した少数の生産者で行われており、ほとんどは日本輸出向けである。 |
|
|
|
|
| ●日本人研究者の案内で |
 「地球の割れ目」とも言えるフィヨルド。かつて氷河が切り刻んでいった爪跡である。私たちの視察先ベルゲンは、フィヨルド観光の入り口だ。ここから奥地に続くフィヨルドを横目に、一行は観光客など一人も訪れたことのない水産研究所のあるアウストヴォル島に向かう。フェリーでおよそ1時間。フェリーは漁業者や買出しの島民をのせて、穏やかな海を進んでいく。 「地球の割れ目」とも言えるフィヨルド。かつて氷河が切り刻んでいった爪跡である。私たちの視察先ベルゲンは、フィヨルド観光の入り口だ。ここから奥地に続くフィヨルドを横目に、一行は観光客など一人も訪れたことのない水産研究所のあるアウストヴォル島に向かう。フェリーでおよそ1時間。フェリーは漁業者や買出しの島民をのせて、穏やかな海を進んでいく。ここの研究所は、ノルウェー国立水産試験場(500人の研究者と職員で構成されている)の臨海支部で、40人体制で研究を続けている。建物内には教授たちの個室がずらりと並ぶ。  説明をしてくれたのは、所長がアメリカ出張中のため副所長のベルギット・ノーベルフ氏(女性)と研究員のシューヴォーゲ・スコール氏。隣接して高等技術専門校もあり、ノルウェー水産技術の層を厚く保つ役割を担っている。 説明をしてくれたのは、所長がアメリカ出張中のため副所長のベルギット・ノーベルフ氏(女性)と研究員のシューヴォーゲ・スコール氏。隣接して高等技術専門校もあり、ノルウェー水産技術の層を厚く保つ役割を担っている。ノルウェー国営放送も「日本の議員がやってくるのは初めて。何の目的なのか」と、昨夜のうちから興味を示している。 (写真は、ベルギット副所長) |
|
|
|
|
 ここの研究所がテーマとしているのは、海水魚及び貝の養殖技術。特にタラとオヒョウを対象としている。最近ではホタテの研究も進めているようだ。ちなみにノルウェーでは、魚と言えばタラであり、それ以外の魚種はほとんどが輸出用だ。 ここの研究所がテーマとしているのは、海水魚及び貝の養殖技術。特にタラとオヒョウを対象としている。最近ではホタテの研究も進めているようだ。ちなみにノルウェーでは、魚と言えばタラであり、それ以外の魚種はほとんどが輸出用だ。(写真は、研究施設・養殖施設へのウィルス持ち込みを阻止するための消毒風景。市内では、いくつかの養殖場がウィルス感染で壊滅的打撃を受け、閉鎖したところもあるという)  フィヨルドの入り口と言うことで、水深はいきなり深くなる。また適度な海流はあるが外海に面していないので、海は穏やかだ。こうした地の利が養殖研究や養殖業に最適なことは言うまでもない。つまり、欠かせないのは、塩分と水温の安定である。その海水を沖合い1.5キロ、水深150メートルから採取しているという。 フィヨルドの入り口と言うことで、水深はいきなり深くなる。また適度な海流はあるが外海に面していないので、海は穏やかだ。こうした地の利が養殖研究や養殖業に最適なことは言うまでもない。つまり、欠かせないのは、塩分と水温の安定である。その海水を沖合い1.5キロ、水深150メートルから採取しているという。(副所長の案内で、施設内の稚魚を見る池本道議) |
|
|
|
|
 北海道の沿岸漁業は、サケ・マス・ホタテをはじめとする栽培漁業が中心だ。過去の採る漁業から育てる漁業への転換は、これまでの試験研究の成果に負うところが大きい。北海道の栽培漁業は、稚魚を養殖し、その後海に放流するという手法であり、ノルウェーのように収穫するまで管理するというやり方とは違う。しかし共通する部分も当然多く、相互の情報交換が求められている。 北海道の沿岸漁業は、サケ・マス・ホタテをはじめとする栽培漁業が中心だ。過去の採る漁業から育てる漁業への転換は、これまでの試験研究の成果に負うところが大きい。北海道の栽培漁業は、稚魚を養殖し、その後海に放流するという手法であり、ノルウェーのように収穫するまで管理するというやり方とは違う。しかし共通する部分も当然多く、相互の情報交換が求められている。(写真は、タモの重さを実感している小谷道議) |
|
|
|
|
 例えば、光を活用した魚の成長制御である。この技術は北海道では、ヒラメの養殖に採用されているが、当研究所で進められている研究は、タラ、オヒョウに、既に実用化と並行しておこなわれており、かなり進んだものと言えよう。 例えば、光を活用した魚の成長制御である。この技術は北海道では、ヒラメの養殖に採用されているが、当研究所で進められている研究は、タラ、オヒョウに、既に実用化と並行しておこなわれており、かなり進んだものと言えよう。(写真は、光の調整による成長のコントロール。日本でもおこなわれているが、魚種にによっては参考にすべき点も多い) |
|
|
|
|
その後、ビタミンなどを加えた餌を研究所の管理下で生産するようになったという。 (写真は、稚魚の餌を見せる研究員) しかし、オヒョウの稚魚を見る限り、変色や奇形などの発生率が高いようだ。これは水質管理とともに餌による影響が大きいと考えられる。 このあたりの情報交換は双方にとって有益である。 |
| ●今後の課題~健全稚魚の育成と魚病対策の共同研究実現を |
「目的は何か」「成果はあったか」「今後どのような具体的取り組みをするのか」など質問は矢継ぎ早である。 (写真は、テレビインタビューを受ける鰹谷団長) 北海道議会として派遣承認を受けてきた私たちは、当然議会を代表する立場で、北海道の水産業が日本の水産業をリードするという意味で言えば、日本を代表する立場でやってきたのである。両地域の得意とする分野を中心に共同開発研究を進める必要があることを、率直に表明してきた。 |
|
|
|
|
| 当日報道された国営放送西ノルウェー地方ニュース 2003年8月22日18時40分放映(以下はキャスターの発言をビデオより翻訳したもの)  本日アウストヴォルに例のない訪問がありました。日本の中でも有数の水産地方の政治家が国立水産研究所のアウストヴォル研究基地に、養殖の視察に訪れたのです。 日本で最も重要な水産地方、北海道議会議員にすら興味をひくものが多くあります。 スカンジナヴィアを視察し、本日は国立水産研究所のアウストヴォル研究基地に養殖の視察に訪れています。  この点の研究に関しては日本人でも学ぶことはあるようです。 日本はノルウェー産養殖魚の重要な輸出相手国ですが、養殖大国でもあります。しかしその養殖には違いがあります。 副所長「国内からも、外国からも視察団が多く訪れます。しかし日本からの視察団は珍しいです。出来る限りの対応をし ています」  実際のニュースでは、団長のコメントやノルウェー漁業の解説などもしていた。 特徴的だったのは、佐々木恵美子道議に対するインタビューがとてもながかったこと。 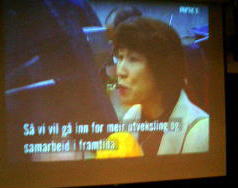 北欧のどの国もそうだが、ここでも、女性の意見を大切にするという国民意識がはっきりとあらわれていた。 |
|
|
|
|
| 帰国したら、水産部との連携もとりながら、道立水産試験場とノルウェー国立水産研究所との連携も模索したい。 |
|
| 前日へ 翌日へ |